|
���Z�H���h �̂����n���h |
 |
����_�s�n���� ���Z�� |
�@���Z�H���h�̂����u�n���h�v
|
���Z�H���h �̂����n���h |
 |
����_�s�n���� ���Z�� |
�@
| �@�u���Z�H�[�Q�v�͑�_�h�����̓�����i���É�����j����h���o�āA�]�n���֗��w�m�ՁA�O�ˈꗢ�ː��A�O�ˏ隬�A���q�X�����c�̏���̒����ՁA�����̏�铔�A���n�i���킽��j�̓n���ՁA�K����n��Ǝ�P�䂩��̌��_�Ђƒ����ω����A�āi��ˁj�̋{�V�ՁA�����ꗢ�ːՁA�n���h�������Z�H��A�n���邩��n���h�֓��蒩�N�g�ߒʍs�L�O���U���玛���E�G�̎����Љ�Ɩn���h�{�w�ՁA�n���h�e�{�w�ՁA���`�~�̕�A���`�~�����A���q�X���̒ʂ�s�j�_�ЁA�n���̓n���Ղ̂܂ł��f�o�r�ʒu����Ƌ��ɁA���ē����܂��B |
�@
| �ԍ� | �R���n | �n�� |
| ���Q�|01�@ | �����ꗢ�ː� | ���������S���������� |
| ���Q�|02�@ | �����g�ߒʍs�L�O���� | ������_�s�n�����n�� |
| ���Q�|03�@ | �n���_��(��铔���) | ������_�s�n�����n�� |
| ���Q�|04 | ������ | ������_�s�n�����n�� |
| ���Q�|0�T | �n���h�e�{�w�� | ������_�s�n�����n�� |
| ���Q�|06 | �{���� | ������_�s�n�����n�� |
| ���Q�|07 | ���䎛 | ������_�s�n�����n�� |
| ���Q�|08 | �n���h�{�w�� | ������_�s�n�����n�� |
| ���Q�|09 | �n�������(���j������) | ������_�s�n�����Ґ�� |
| ���Q�|�P0 | ���F�̓n���� | �����H���s���F�������F |
| ���Q�|�P1 | ���F�ꗢ�ː� | �����H���s���F���P���� |
�@
�@
�@
��ϊ�蓹�����܂������A���Z�H�̓����u������Ձv�܂Ŗ߂���Z�H��n���h�i�݂����Ǝv���܂��B
|
���Q-11
���n�̓n���� ��_�s�����ƈ����S�n������ |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���n�i�K���j�̓n���� �@�����Ă��̂�����̗K�������n�i���킽��j��Ƃ����A���Z�H�̓n�D������n�̓n���Ƃ����܂����B �@�앝�͂T�O�ԗ](��X�P���j�n�D�Q�z�A�L���D�Q�z�A�D���͂P�O�l�A���R�⒩�N�ʐM�g�̒ʍs���ɂ́A�W�O�z�قǂ̑D�����Վ��ɉ˂����܂����B�@�i���݂̒��ǐ�勴���R�X�O���̒����ł��B�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��{�s�������j���������فj |
|
�Ί݂ւ͉����i���P�O�Q�O���j�ɉ˂���K��勴��n��܂��B
|
���Z�H�0�T/15 |
|
|
|
���Z�H�S��Ԃ�15��Ԃɕ����Ă��ē����܂��B(�{�}�͂T��Ԗڂł��j |
���n�̓n���i�K���j�𐼌��֓n��܂�
|
���Q-12 ���n�̓n�����(����) �����S�n�������� |
|
| �����̒�h��ɂ͓n����Ղ������Ђ�����܂����B | |
��h�������ƌ��_�Ђ�����܂��B
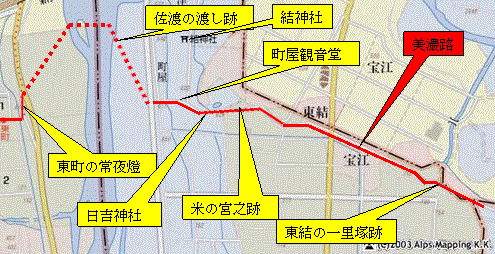 |
|
���Q-13 ���_�� �����S�n�������� |
|
|
���q�X�������ɑ��������Q�� |
�@ |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ǝ�P�����ꂽ�u���_�Ёv |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���_�Љ��N �@���̒n�͑����̑�{�l�A���m�A���m�̋F������߂�ꂽ�É̂��c���Ă���܂��B �@�@�i���̍��i�P�S�R�O�j�Ǝ�P�͌��喾�_�ցA�����ԋF�肵�A���I�����ƍĉ���{���ꐡ�����̉��������̎Ђɔ[�߂��܂����B�i���̎��{���������ω��̖{���Ɠ`�����Ă��܂��j �@�V���O�N�i�P�T�V�T�j�D�c�M�������喾�_�ցA�����ԋF�肵�A������������Ɠ`�����Ă���܂��B �@������N�i�P�W�Q�U�j�z�O�̍��i���䌧�j�I�]�ˎ� �ԕ����́A���̓r�� ���喾�_�̉��n��������������Ƃ�[���p�����������i�݂��炵���j����i���܂����B �@����R�U�N�̗K������C�ɂ��A�������́A�͐�~�ƂȂ�A���ݒn�ɑJ���\���グ�܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�����ł��j |
|
 |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������w�蕶�����@ ��A�����E�_���Q�i�{�a���j �@�@�@�召�\���̂̐_���Q�ŁA��������ؒ��ł���B���̐_���͌�_�̂ł͂Ȃ��_�Ђɕ�[���ꂽ�@���_�ł͂��邪�N��̌Â��Ǝv������̂����茋�_�Ђ̗��j�����M�d�Ȃ��̂ł���B ��A�����Α������i��j�{�a�� �@�]�ˎ���O���O�S�\���N�O�����ܔN �@��i�@�ԑ��؍��q�� |
|
���m�Ȉʒu�͕s���ł��B
|
���Q-14 ���隬 �������S���������� |
|
|
���隬�ƕt�߂̏隬���c��Y���q�̊ق����_�Ђ���쐼700m�̒n�ɂ���܂����B |

|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@����̗��j |
���_�Ђ����W�O���قǓ��ɒ����ω�������܂��B
|
���Q-15 �����ω� �������S�������������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���j�̓� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���q�X�� �@�����炨�悻���S�N���炢�O�̂��Ƃł��B�@�����������q�ɖ��{���J���ƁA���s�Ɗ��q�����ԓ��H����������܂����B �@���s���瓌�R����ʂ��Ĕ��Z�̍��ɓ���A�s�j�S�̐�h��������������E�����E�n������c��ʂ��h�Œ��ǐ��n���ĉH���s��ʂ�����̍��i���m���j�̍��c�E���Â��o�ē��C���֓���A���q�֒ʂ��邱�Ƃ��犙�q�X���i���Z�H�j�Ƃ��Ă�A�����͍ł���ȓ��H�ł���j�Ձu���q�X���v�u�ꗢ�ːՁv���c�铹�ł��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̒n��ҍ��i�����j�Ƃ����R�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ǝ�P�䂩��̒����ω��� �@���̏\��ʊω��͐������q�̍��̐�h�̖Œ������ꂽ�ω��ŁA����̈ꐡ�����i��U�a�j�̉������͏Ǝ�P�̎�{���ł���܂��B |
|
�X�ɓ����P�T�Om�قǐi�ނƉE���ɓ��g�_�Ђ�����܂�
|
���Q-16 ���g�_�� �������S���������� |
|
| �ڂ����R���͕s���ł� | |
�X�ɓ����W�O���قǂ̍����Ɂu�Ă̋{�V�Ձv
|
���Q-17 ���i��ˁj�̋{�V�� �������S���������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�Ă̋{�V�Ձv�i��˂݂̂�j �@�u�������҂̖T�ɐ̂�肠��A���l�̋{�Ƃ�����ɓ]���ĕĔV�{�ƌ����A�]�X�v�Ɛ���������܂��B�@ |
|
�u�Ă̋{�V�Ձv�����V�W�O���قǓ��i�ނƒ�h���牺��铹������A���̓�������܂��B
��h���ɓ����Ԃ̈ꗢ�ːՔ�ƒn����������܂��B
|
���Q-18 �����̈ꗢ�ː� �������S�n��������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������j�Ձ@���Z�H�ꗢ�ː� �@�c����N�i�P�U�O�S�j���㏫�R����ƍN�́A�]�˓��{�����N�_�Ƃ��Ď�v�X���̈ꗢ���ɒ˂�z���܂����B�@��ɘe�X���ɂ��y�ڂ��A�˂̑傫���͌܊Ԏl���i�X�b�l���j����ŁA�˂̏�ɂ͉|�i���̂��j�⏼�Ȃǂ�A���ė��l�ɕX��^���܂����B �@�́A�������������Ɏ����P�C�R�O�O���̊Ԃ́A���h�ȏ����ł���܂����B �@���́u�����݂��Ⴕ�Ⴍ��v�Ƃ����ċȂ��肭�˂��Ă��܂����B �@�O���̂Ƃ���Ɂu����_���v�V������ׂ������Ă��āA���̗����Ɉꗢ�˂�����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����������ψ���j �@�n�����̑���Ɂu�E �n�ҁ@�� ��_�v�ƍ��܂�A�e�ɂ́u���Z�H�@�ꗢ�ːՁv�̐Δ肪����A���̓�k�Ɉꗢ�˂�����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��{�s�������j���������فj |
|
�����V�ꗢ�ːՂ����h��֖߂�X�ɓ����P�����قǐi�ނƒ�h���։���铹������܂��B
��h���։���܂��B�n���h�֓��鐼���ł��B
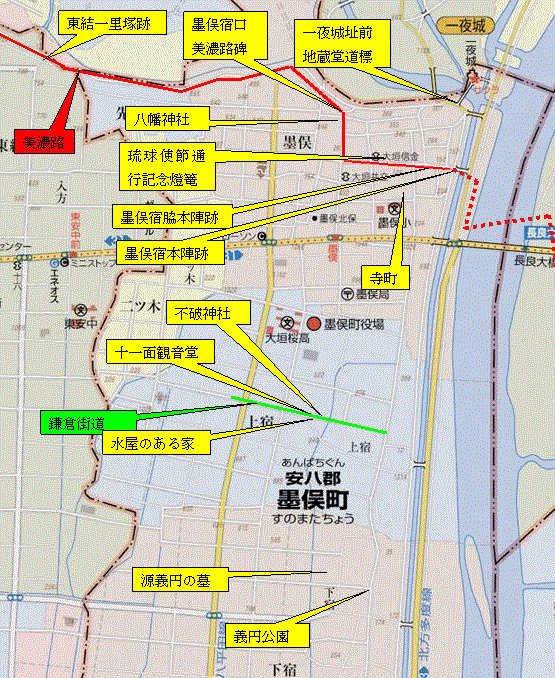 |
|
���Q-19 ���Z�H�� �������S�n���������� |
|
|
�h�֓����h���Ɂu�j�� ���Z�H�v�肪����܂��B |
|
��̑O���֓���܂��B
 |
�u�J���R���Ǖ��v �@���炭����ƈɐ��R�������Ɍ����Ă��܂��B �@�J���R���̔肪�X���e�ɗ����A�����k�֕�����܂��B �@��̋��ɂ��u�J���R�֘Z�����v�̕����������܂��B �@�Z�����͖�26km�A6���Ԕ��̋����ł��B �@�r���A�x�e�������Ɩ�W���ԁA�قڂP���̃R�[�X�ł��B |
 |
| �P�O�N�O�ɖK�ꂽ���̉摜�ł��B�����������ł� | ||
�h�֓��炸��h��𓌂i�ނƖn�����j�����فi���隬�̌��V��t�^�̌����j
|
���Q-20 ����� �������S�n�����n������V�z |
|
| �����R�N�ȑO�����隬 �@����͉J�I�����̂�����x�̏����ƌ��������̘E�╻���ŏ�Ƃ͂����Ȃ������ȍԂł����B �@��ڂ��I�������͍r���ɔC������Ԃł����B ������_�� |
 |
|
| ����̉摜�͗��j�����ق����O�̈��隬�̗l�q�ł��B | ||
|
���j�ɂȂ��V��̏� �@���隬�ɓˑR�P���V��B �@�{���̈���͑e���ȋ}�����炦�̍Ԃł����B �@���̊ό����ƂƂ͌��������\���Ɏv���܂��B �Ó���3km�͒�h�̏� �@�u��Ԑ_�Ёv����A�܂��u���隬�v�t�߂֏o�Đ��ցu�Ґ�v�̒�h���i�݂܂��B �@�^������X������邽�߂ł��傤�B |
|
��قǂ̒�h���́u���Z�H��v����h���֓���܂��B
|
���Q-21
����O �H���s���ؒ��{�� |
|
|
�R�������� |
|
�@
|
�n��(���̂܂�)�h |
|
�h��̊T�v ��_�˗́A�@�h���@�s���A �h���@�V���V��(���V�V�U���j�A�@�l���@1�A�Q�P�W�l�A�@�Ɛ��@�Q�U�R���A�@ ���ā@�P�P���A�@�{�w�@�ꌬ�A�@�e�{�w�@�ꌬ�A�@�≮��@�P�P���A�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��_�h����@�\�ԁi��V�C�Xkm�j�i�O�ˈꗢ�ˁE�����ꗢ�ˁj �N�h�܂Ł@�\������\�܊ԁi��X�C�Wkm�j�i�����F�ꗢ�ˁEf�s�j��F�ꗢ�ˁj |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���h�i���̂܂����キ�j �@�Z�B�m�s�L�͍]�ˎ���́u���̂܂��v�̒������悭�`���Ă��܂��B �u���̒����������ԁi830m�j����A���̖����͒[�������{�������������Ƃ����B�X���݂͑�̂悫���Ȃ�A������{���̊ԁA���ĉ������B�{�w�͒����ɂ���B�_�Ƃ̊O�ɂ͏h�����������������Ȃēn���Ƃ���悵�B�����͊F�A���ǐ�̒�h�ɂ���Či�F�悵�B�k���ɏ��S��������A�����a���Ƃ����B�����̖k�A�Ґ���ɂ����Ƃ���v�ƋL���Ă��܂��B �@���̋L�q�ɓ���Ėn���̒�������ƕ��i�͂قƂ�Ǔ����ł��B �Ɛ���S�Z�\�O�� �@���a��N�i1802�j�̋L�^�ɂ��ː�263���A�l��1,218�l�Ƃ���܂��B �@�����i���������j���x�Ɏx������č]�ˎ���̖n���͏h�꒬�Ƃ��Ĕɉh�����̒n��̌o�ϥ�����̒��S�n�ƂȂ�܂����B �@�������x���喼�s��ȂǑ����̐l�肪�v��Ƃ��́A����̑�����l�n�Ȃǂ̎�`�����o�����鐧�x |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���h�[�Q �@�n���h�Ƃ����A�퍑����ɖ؉����g�Y�i��̖L�b�G�g�j���z��������ŗL���ł����A���q����ɂ͊��q�Ƌ��s�����ԊX���Ƃ��Đ������ꂽ���q�X������h�Ɠ�c��ʂ�ȂǁA�Â������ʂ̗v���ł����B �@�������́u�\�Z����L�v�ɁA�����O�N�i�P�Q�V�V�j�n���̒��ǐ�őD����n�����L�q���c���Ă��܂��B�]�ˎ���̔��Z�H�ɂȂ��Ă�����A�n���̓n���ɁA���R�⒩�N�ʐM�g�̒ʍs�̍ہA�K���A����A�ؑ]��ƂƂ��ɗՎ��ɑD�����˂����܂����B �@�V�ۏ\�l�N�i�P�W�S�R�j�̖n���h�ɂ́A�Ɛ��R�R�W���A�l���P�C�R�P�V�l�A���ĂP�O���i��U���A���S���j�A�{�w�E�e�{�w�e�P���A�≮��P����������܂����B �@�������㖖���ɂ́A�X������h���璆���A�{���A�����Ɉڂ�A�c���N�ԁi�P�T�X�U�`�P�U�P�T�j�����ɖ{�w���u����܂����B��������s�Y�����Ƃ����A���ڈȍ~��X���F�l�Y�𖼏��A�����܂łP�R�㑱���܂����B �@�w�Z�B�m�s�L�x�ɂ́A�u����B���̖����͒[�E�����E�{���E�����E�����Ƃ����B �@�����݂͑�̂悫���Ȃ�B�@�����E�{���̊ԗ��đ����B�k���ɏ��S��������B�����a���Ƃ����B�����̖k�Ґ���ɂ����˂���A��������m�˂Ƃ����B�v�Ƃ���܂��B �@�܂��A���̂����₩�ł������Ƃ��`�����Ă���A�X������������Ƒ����̎��@��j�Ղ��c��h�꒬�ł��B |
������h�֓���Ɛ悸�����_�Ђ̑O��ʂ�܂��B
|
���Q-22 �����_�� �������S�n���������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������{�R�� �@���̔����{�̓�Ɋ��q�X��������A���Z�H�͒����̑O��ʂ�A�����E�����ʍs�̗v�Ղ̒n�ł���܂����B �@�]���Ē������茹���̕�����D�L�̐퍑����̕��l�����������ΎQ�w�ɖK��܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ȉ��ǂݎ��s�\�@���n�������j�@ |
|
���Z�H�͔����_�Ђ����P�U�O���قǓ�i��Ŏl���H�𓌂Ȃ���܂��B
�����ē����P�P�O���قǂ̒n���M���ׂ̗ɒÓ��_�ЂƏH�t�_�Ђ�����܂��B
���̒Ó��_�ЂƏH�t�_�Ђɗ����g�ߒʍs�L�O���Ă��ڒz����Ă��܂��B
|
���Q-23
�����g�� �����S�n�����{�� |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����g�ߒʍs�L�O���U |
|
|
�ђ쒌�̊��|�̕��� �u��铕�v�u�����V���v �@ |
�@�@�@�@�@�@�Ó��_�Љ��v �@���m���Ó��s�A�Ó��_�Ђ̕��g�Ɠ`���A�n���N�I�͕s�ځB �@���u�_�Ƃ��Č����M������A�����O�N���� �������g�߈�s�ʍs�̍ە�[����Γ��Ăɍ��������肢�A�V�q���̖щ��������M����B �@�@�@�@�@�@�@�@�i���n�������j |
�Ó��_�Ёi�����g�ߒʍs�L�O���āj���瓌���W�Om�قǂ̖k���̎l�҂��i�E�j�Ȃ���Ǝ����֓���܂��B
|
���@�� |
| �@�@�@�@�@�@�@�����Ǝj�ՁE������ �@�����͂��̖��������Ƃ���A���̋ߍ݂ɂ͒��������@���W�܂�̖̂ʉe���Ƃǂ߂Ă���B �@���Z�H�̏h�w�ɊW���[���A�������E���E���o���E�{�����E�L�ꎛ�͐^�@��J�h��{�R�Ƃ��Ă���B �@���䎛�͏�y�@���R�T�ю��h�i�ϓ��T�ю����{�R�ł���B �@�e���@�ɂ͎���E�������������B �@���ɖ��䎛�͎j�Ղɕx�ށB�y�ܘY�̕�E���R�z�̕�蕶�E�ē������̕�E�n���{�w�̕�Q�E���Y�Βn������y�֑ɗ��ȂǗ��j�̕��݂�[��������������̂�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���n��������j |
|
���Q-24 ���� �����S�n�������� |
|
|
���Q-25 ���o�� �����S�n�������� |
|
|
���Q-26 ������ �����S�n�������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�R�Ƃ��� �@���������n���̖������́A�V�����L�i�ΎR�{�莛���L�A�P�T�R�U�j�ɂ��ƁA���̍��ɂ͖����������A�D�c�M�����U�ߓ��钷������ɂ͑�P�R��ߗS�����u���R�ی�@�v�ƎQ���A���Q���Ă���B �@�V����N�i�P�T�W�P�j�ɂ́A�l�S���J���肤�L�b�G�g���O�S�O�\�̍їW�������Č�A��������̒n�Ɉڂ����B �@���쏉���ɂ͖������\�P���A��ɂ͋�\�Z����������{�R�Ƃ��ė������ɂ߂����A���菉�����Ƃ��Ƃ��Ɨ������B �@�×����Z�O�����̈�F�Ƃ������A���l�u�n����V�v�Ƃ��Ă�ł���B �@���{���u����ɔ@���v�͏t���̍�Ɠ`�����A�F�J���A�����ɂ��@�A���ȂǑ���������B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����R�@�F�J�@�@������ |
|
|
���Q-27 �{���� �����S�n�������� |
|
| �R��͘e�{�w�̖� ���薖�N�ɘe�{�w�̖傪�ڒz����A���݂̎R��Ƃ��Ďc���Ă��܂��B |
|
|
���Q-28 �L�ꎛ �����S�n�������� |
|
|
���Q-29 ���䎛 �����S�n�������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@���Y�Βn���i�͂�������炢�������j�i���䎛�j �@�́A�n����ɋ�������A���������Y�����������߁A���l���@��o���ƁA���n���l�̎p�Ɍ������̂ŁA����J��܂����B �@���̌�A�O�m�i�����ɂ�j�N�ԂɎQ�c����⹌����������Ēn�������������܂����B �@�V�c��N�Ɏ鐝�V�c�����̒n�����ʼnJ�h�������A���l����n���l�̗R�����āA�u�����c��@�^���̉��̋�����@�܂��������ā@�l�n���Ȃ�v�ƌ��̂����ƁA�ɂ������ꂽ�̂ŁA�ȗ��A�u���Y���n���l�v�Ƃ��đ�ɂ��J�肳��Ă��܂��B |
|
�u�n���h�v�͊C����́u�K���v���ʂ���̊X���A�R����́u�J���Q�w�v�X�����W�܂�Ƃ���ŁA
�X���ň�Ԃ̗V�s�Ȃǂ��������A�ɂ��₩�ȏh�ł����B
|
���Q-30 �n���h�e�{�w�� �����S�n�������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�e�{�w�� �@�e�{�w�͐̂̂܂܂Ō������܂��B �@�e�{�w�͕��ʂ̏Z��Ƃ��Ďg�p����Ă��邽�߉����̏�ɃN�[���[�̉��O�@���������肵�܂����A���ւ��ʂɂ���̖̂ʉe���ł��邾���c���悤�z������Ă��܂��B |
|
|
�O�����{�ɂ͏h��S�̂ł萗�Ղ肪�s�Ȃ��e�{�w���J������܂��B |
|
�e�{�w�����W�O���قǂ̓���h�̎�O��p���n���h�{�w�Ղł��B
|
���Q-31 �n���h�{�w�� �����S�n�������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�w�� �@�n���������̒�h�p�ɂ������{�w���������͂Ȃ��B �@�c���N�Ԃɏ���u����s�Y�����v�A���ڈȍ~�͑�X���F�l�Y�𖼏�薾���Ɏ���܂ŁA�\�O�㑱���܂����B �@���̊ԂɓV�c�̒��g�A�e�˂̑喼�A�܂����N�◮���̎g�߂��h������Ȃljh���܂����B |
|
|
��h�ォ��n���h������ |
|
���Q-32 �n���h�� �����S�n�������� |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���h�u���Z�H�v �@���Z�H�͓��C���̔M�c���番����A���É��A���F�A��t�A�����A�N�A�n���A��_�̎��h���o�Ē��R���̐���h�Ɏ���e�X���ł��B �N����\�����i��10km�A�]�˂���͋�\�����\��(380km��10����/1������12���Ԃ̋���)�̈ʒu�ɂ���܂��B �@�喼�̒�h�Ƃ��Ė{�w�A�e�{�w������A�h���l�n�̗�����Ɩ��Ƃ���≮��A�n���n���̓n���ꂠ��A�œ��₩�ł����B |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n���h��Ǝj�Ձu���Z�H�v�� �@�n���͌|�҂̒��Ƃ��Ă��L���ł����B �@�Â����ォ��n�D��Ƃ��ďd�v�n�_�ł���A�����x�e���A�h�������������ƌ����Ă��܂� �@��������ɂ͒��җV���̖{���ƂȂ�A���q����ɂ͊��q�X���̏h��ƂȂ�A�ɐ����ɂ߂܂����B �@�]�ˎ��㒆���ɂ͔ѐ������l�������ꂽ�̂��A�h��Ƃ��Ă��V�s�Ƃ��ė��l�̕]���ƂȂ�A���̓`���͖������߂����a�����܂ő����܂����B |
|
�{�w�Ղ̒�h���H���i�ނƁu�����n����̍���v�Ղƌ��`�~�i�݂Ȃ��Ƃ�����j�̕�Ȃǂ�����܂��B
�{�w�Ձ`����P�����قǂ̒n�_�Ɍ��`�~�����Ղ肷��u�`�~�n�����v�Ȃǂ�����`�~����������܂��B
|
���Q-33 �`�~���� �����S�n�������h |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����n����̍��� �@�{�a���N�i�P�P�W�P�j���ǐ���͂���Ō����̑匃�킪�W�J���ꂽ�B �@���ɂ��������n����̍���ł���B �@���N�l���������a�����B �@���������͐��āA���֍U�ߏ��B �@������}�������߁A���d�t�叫�Ƃ��Ĉې��E�ʐ��E���x�E�m�x�E���j�E���v�Ȃǂ̕�������]�R�Y�����n��A�E�݂̖n�����i�㉺�h�j�ɐw���B �@��������̏��s�Ɓi�V�{�\�Y���l�j�͐�]�R�𗦂��č��݂̉H�����ɒ��w���B �@�������͉����̂��ߒ�̌��`�������A���コ���������������A�Q�����u�ĂČR�𐮂����B �@�`�~�͍s�Ƃɐ�w����Ă͌Z�����ɍ����炪�Ȃ��ƍl���A�B��l�n�ɏ��A�G�w���̐��݂ɂЂ��݁A�閾���ƂƂ��Ɂu�`���͍����̑叫�Ȃ�v�Ɩ�����Đ�w�̂������������悤�ƁA���ޖ閾����҂��Ă����Ƃ���A������x���Ɍ��Ƃ��߂��A�u���q�������̒�ŋ��̌��`�~�Ƃ����҂��v�Ƃ������������E���ɐ킢�A���^���Ȃ��A�͐s�������j�ɓ����ꂽ�B �@�����͐험���炸�A���������̐Y�d���Z��@�������A�s�Ƃ̎q���Y���ƌZ��͕����x�ɕ߂炦��ꂽ�B �@�s�ꂽ�����͑ނ��A��i��͂��j��̓��݂܂őނ����������̑啺����Ɛ�`�����肩�����Đ��ɕ��Ƃ�S�ڂ����ƂɂȂ�B �@���`���͗����ٕ̈��̒�ŋ`���i�������̕��j�̏���Ռ�O�̎q�`�o�Ɠ����̌Z�ɂ�����B �@�c��������Ƃ����A�V�����ɗa�����Ă����B �@�Z�̋������A��b�R�̑m���̂��Ƃ��V�哪�Ђɕ�݁A�����̈߂𒅂Ċ��q�삯�����Ǝv����B �@�n����̍���Ŕ߉^�̐��U������B�@��\�܍ł���B �@�i���������L�E���ƕ���E��Ȋӂ��j�@ �@���l�͋`�~�n�������݁A�������āA���N�O���\���ɋ��{�𑱂��Ă���B �@������S�\�Đ��ɕ悪����B �@���a�\�Z�N�O���\���ɔ��S�N�Ղ��s�Ȃ�ꂽ�B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����S�n�����j ���̐킢�Ŕs�k���������R�͓��֔s�����܂��B |
|
���`���i�݂Ȃ��Ƃ̂�����j�Ƃ́H
|
�����̌n�}�i���`�Ƃ���l��܂ł̔����j |
|
�u���ƌ��Ǝj�Տ���v�i23pro.tok2.com/freehand2/rekishi/keizu-genji.htm���Q�l�ɂ����Ă��������܂����B |
|
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����A���i�̗� �@�����A���i�̗��i�����傤�A���ウ���̂��j�́A�������㖖���̎���4�N�i1180�j���猳��2�N�i1185�j�ɂ����Ă�6�N�Ԃɂ킽���K�͂ȓ����ł���B �@�㔒�͓V�c�̍c�q�ł���Ȑm���ɂ�鋓�����_�@�Ɋe�n�ŕ������𒆐S�Ƃ���Z�g�������Ƃ����镽�������ɑ��锽�����N����B �@�ŏI�I�ɂ́A�������͓��m�̑Η�����������������̕���ɂ�茹�����𒆐S�Ƃ�����ɍⓌ��������\�������֓������i���q���{�j�̎����Ƃ������ʂɎ���B �@�����������̓��N�[2���ɁA���������M�a�Ŗv���ĕ��������͋��͂Ȏw���҂������B �@�������A�����3���A���������͍Ăѓ��C���֒Ǔ��R��h�����A�����n�����Ŋ֓������R�Ɖ�킵�ĕ����R�����������߂��i�n����̐킢�j�B �@���̌��ʁA�����R�ɂ�铌�C�����ʂ̐i���͈ꎞ���f���邱�ƂƂȂ�B �@ ���������Ƃ͂��̔N���犈���������k���̔����Ɛ��̖͂I�N�͌��߂������Ƃ��ł����A�W���ɕ��ʐ��A�o�������Ƃ���R��h������B �@�������A�ʐ��ƌo���̘A�g����肭�����Ȃ���ɁA���ƕs���ɂȂ�܂��ꂽ���Ƃ͖k���n���̔�����������邱�Ƃ��ł����ɖk������P������B �@���̔N�A���s�ł́u�{�a�v�Ɖ������ꂽ���A�����甽�������͂͂����F�߂��Ɏ����̌�����p�����B�@���̔N���痂�N�ɂ������{�a�̋Q�[�Ƃ�����Q�[���N�������Ƃɉ����A���������͈����V�c�̑另�Ղ̎��{�i11��24���j��D�悵�A�����R�������������ɕ����̗��͖̎Ƃ��Ă��炸�A�㗌�̂��߂̐����I�A�R���I�����𐮂��鎞�Ԃ��K�v�ł������B �@��������̓��L�w�ʗt�x�ɂ͂��̔N��8��1�����ɂāA�捠�㔒�͖@�c�̌��ɗ����̖��g������ꂽ���Ƃ��L���Ă���B |
|
|
|
���`�~�i���j���{�� |
�j�� �����n������� |
|
�`�~�n���� |
�`�~�����̐��P�T�O���قǂɌ��`�~�̕悪����܂��B
|
���Q-34 ���`�~�i������j�̕� �����S�n�������h |
|
|
�`�̎��ɏ���ꂽ��̕W�� |
�c��̒��ɍ����c���� |
�`�~�����̖k�P�O�O���قǂɊ��q�X�����c���Ă��܂��B�ڈ�͐������ł��B
|
���Q-35 ������ �����S�n�������h |
|
�������̐��ɕs�j�_�Ђ�����A���̋����Ɋ��q�X���肪����܂��B
|
�p�\�̗��`�������� �����S�n�������h |
|
| �@�@�@�@�@�j�ՁE�`���ē��@��C�l�c�q�ƕs�j���_ �@�����U�V�P�N�V�q�V�c�����B �@��ɋg��ɓ��Ă������{�ł����̑�C�l�c�q�i�V���V�c�j�Ƒ�����b�ł����q�̑�F�c�q�i�O���V�c�j�̊Ԃɍc�ʌp���̑������N�����B�@�p�\�̗��ł���B �@�����W�����Ɛ������ɂ�����ő�̔ߌ��ł���B �@��C�l�c�q�͑�Ë{������A�g��ɓ��ꂽ���A�X�ɐg�̊댯�������ɉ�A�鎭��蓌�{�̗̒n�ł�����Z�ɓ�����B �@�]�����̂�鸕��]�Ǎc���i���̂̂���̂Ђ߂��j���͂��ߓ�\�l����B �@�����œG�ɏP��ꂽ�����������Ȃ��B�����̂�����Z�܂ł͉��Ƃ����ꂽ���Ƌ��s�R�������B �@���̌�A�������S�̓����ߑ��b�i��ɍ����ĕ����W�߁A�s�j�����ߍ]�ɓ���A��F�c�q���łڂ��A��䌴�ɑ��ʂ��ꂽ�B �@�F���̈╨��Ɂw��C�l�c�q�n���ɓn�ɂē�ꂽ�܂��x�ƋL���Ă���B �@���̈�߂������Ɓw���̍��̏B���̂킽���ɏM���Ȃ������Ă���ꂽ�B�����傫�ȓ��M�ŕz�����Đ���Ă���Ƃ̂����āA�u���Ƃ����ēn���čs���������v�Ƃ�����ƁA���́u������F�̌�g�Ƃ��ӂ��̂����āA�n�M��̏M���݂ȉB���čs�����̂ŁA������n���Ă������̓n�D���ʉ߂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�������Ęb�����Ă��邨�邤���ɍ��G�R���U�߂ė���ł��傤�B�ǂ����ē�����܂����v�Ƃ����A�u���Ăǂ�������悢���v�Ɛ\�����ƁA���̏��������̂́u���Ȃ���q������Ƃ����l�ł͂Ȃ��M���l�̂悤�ł��B�ł͂������ĉ������v�ƌ����āA���M�����Ԃ��ɂ��āA���̉��ɕ������āA��ɕz�𑽂��u���āA�����݂����Đ���Ă����B �@�@���炭���ĕ��@�ܕS�l���藈�āA���ɖ₤�Č����B�u�������l���n���čs�������v�Ƃ����A���́u�M���l���R����l���藦���Ă���ꂽ�B�����͐M�Z�̍��ɓ����Ă�����ł��傤�B�f���炵�����̂悤�Ȕn�ɏ���Ĕ�Ԃ悤�Ɍ������B���̏����ŒǕt���Ă��F�E����Ă��܂��ł��傤�B���ꂩ��A���ČR�𑽂������Ēǂ��Ƃ悢�ł��傤�v�Ƃ����ƁA�{���ɂ������v���đ�F�̍c�q�̕��͈����Ԃ����B �@���̌� ��C�l�c�q�͏��ɋ�����ɂ́u���̕ӂŌR�����W�߂������o���Ȃ����낤���v�Ɩ����ƁA���͂���܂ǂ��āA���̍��̂ނ˂Ƃ�����̂ǂ����W�ߌ�荇���Ɠ�A�O��l�̕����o�����B �@���������đ�F�c�q���ߍ]����Âɒǂ������łڂ��ꂽ�B �@���̂��̂܂��̏��͕s�j���_�̉��g�ł���Ɠ`�����Ă���B�x�@�@�i�s�j�_�А������j |
|
 |
| �@�@�@��C�l�c�q��鸕��]�Ǎc���Ɩ�t�� �@�ޗǖ�t���͕a�C�̍c�@�i鸕��]�Ǎc���A�̂��̎����V�c�j�̂��߂ɁA�V���V�c(��C�l�c�q�j�����Ă悤�Ƃ��������ł���B����͓ޗǂɓs���ł���O�\�N�O�̂��Ƃ������B �@��t�������Ă͂��߂�����A�K���ɍc�@�̕a�C�͕����A�Ƃ��낪���x�͓V���V�c���a�C�ɂȂ�A���ɖS���Ȃ��Ă��܂��B �@�����V�c�́A�S���Ȃ����V���V�c�������v�炵�A��u���p���Ŗ�t���������������B �@��t���́A���߂͓������i�ޗnj������s�j�Ɍ��Ă�ꂽ���A�J�s�ɂ��A���鋞�Ɉڂ��Ă����B �@�����͎O�d���B�����������̉��ɂ��ꂼ��֊K�i�������j���t���̂ŁA�ꌩ����ƘZ�d���ɂ݂���B�傫�ȉ����̉��ɏ����ȏ֊K�B �@�x�d�Ȃ镺�ɂ����蓖������c��͓̂����i��O�j�݂̂ł��B |
|
�u�Ó��v�̎n�܂� |
�s�j�_�Ђ̐��ׂɏ\��ʊω���������܂�
|
���Q-37
���q�X���Ɓ@�@�@�@ �����S�n�������h |
|
 |
 |
|
���q�X�� |
�̂͊ω����O�Ɋ��q�X���W���� |
| ���q�X�� �@���ǐ�Ȃ́u�n�����v����K���Ȃ́u�����v�܂łɊ��q�X�����c���Ă��܂��B ���q�X���͊��q����A���������u���q���{�v���J�������ɁA���q���狞�s�܂Ő��������u�����v�ŁA���܂��܂ȕ����̍s�����������Ƃ��ė��j�I�ɂ��M�d�ȊX���ł��B
�X���͖n���u��h�v���� |
�u�p�\�̗��v�Ƃ� �@�փ���������ȑO�ɁA�Ñ���{����V�������ڂ̐킢���u�p�\�̗��v�ł��B �O�� �@���̓V�c�u�V�q�V�c�v�͍c�ʌp���҂��c����i�������������V�c�̒�j�̑�C�l�c�q�i�������܂̂������j�Ɍ��߂Ă��܂����B �@�������A���炭���Ď��q�̑�F�c�q�i�����Ƃ��̂������j�ɍc�ʂ����肽���Ȃ�A671�N�P���T���ɐV�����|�X�g�u������b�v�i�����傤��������j������F�c�q��C�����܂����B �@����ȍ~�A�@��C�l�c�q�𐭌����牓�����悤�ƁA���낢����ł��܂����B �@�������A�Ԃ��Ȃ��V�q�V�c�͕a���ɕ����g�ƂȂ�A�����ɑ�C�l�c�q���Ăт��Ƃ�����܂������A��C�l�c�q�́h�A�d�h�������A������Ŏ����o�Ƃ��A�ȁi��̎����V�c�����Ƃ��Ă�̂��j�A�q�ƂƂ��ɋg��ɉB�����c�ʂւ̖�S�̂Ȃ����Ƃ����Ɏ����܂����B ���n �@�V�q�V�c�͍c�ɓV�c�A����c�q�A���b������Ɩd��A�h��ڈΥ�������q���E�Q���剻���V�i645�N�j��f�s���f���̌y�c�q��V�c��F���V�c�Ƃ��A����͍c���q�Ƃ��Đ����̎���������V�c���̊m���Ƃ����������v�𐄐i���A�r�����Δh�̌Ðl��c�q�ƗL�n�c�q�Ƃ��E�Q���A��Ɏ��炪�V�c�ɂȃ��܂����B ���u�� �@671�N12���V�q�V�c���v���A����s���̒��A�g�̊댯����������C�l�c�q�͋g���E�o���A�����̗̓y�̔��Z�֒��錓�s�ňɉꥈɐ��������Z���s�j�i�փ����j�܂ŋ}�����B �@�����ɍs�{�i���傤�������{�w�j��u���A�W�߂������Q�R�ɕ����A�@��𐧂���ꂽ��F�c�q�R���U�߁A���c��܂Œǂ��߁A��Ë����ח������܂����B ���Q��Ɠ��z�R �@��F�c�q�͒����R�ɂ����Ď��Q����A���̌�́A�s�j�̍s�{�i�{�w�j�ɉ^�������̌�A�����A���Q��Ƃ��Č��݂��`�����Ă��܂��B�i���R���E�s�j�̊ցE��Ռ�O���̊��ɏڍׂ���j �@�܂��A����ƍN���փ�������̎��A�ŏ��ɐw�����u���z�R�v�̌ď̂͂��u�p�\�̗��v�̎��� ���̒n�œ���z���ĕ������サ���Ƃ��������`�����痈�Ă��邻���ł��B �@�ƍN�����́A�̎��ɂ��₩���āA���ʂ��̈������́u���z�R�v�ɐw��u�����̂����m��܂���B�i���R���փ����h�ɏڍׂ���j ���ߑ̐����� �u�p�\�̗��v�ɏ������A���͂ōc�ʂɏA������C�l�c�q�́u�V���V�c�v�ƂȂ�V�c�̐_�i������ߑ̐��̐����𐄂��i�߂܂����B |
|
�\��ʊω����̌������ɂ��̒n���ŗL���� |
| ���̂�����̂��������̖��� �@���̕ӂ肩�牺���ɂ����ẮA�x�d�Ȃ�^���ɔY�܂��ꉮ�~�������Ί_�̏�ɍ����邱�Ƃɂ��܂����B �@���������قǍ����ςݏグ���������A����̎ԎЉ�ł͉����Ƌ�J�������悤�ł��B ���� �@�����̂Ȃ��Ƃ͗���ȂLjꕔ���������āA�����ɐ�����A���~�A�M�d�i��u�������ɂ͏M��݂�����ɔ����܂����B |
�n���h�܂Ŗ߂蒷�ǐ�̒�h�܂ŏ��܂��B
�n���̓n���Ղ͒肩�ł͂���܂��n���h�Ə�h�̒��ԕӂ�Ǝv���܂��B
|
���Q-38 �n���̓n���� �����S�n������h |
|
�n���Ղ͍^����͐���C�̂��߁A����炵�����͉̂�������܂���B
���ǐ��n���ĉH���s�֓���܂�
|
���Q-39 ���ǐ�n�D �@ |
|
|
�n���̐Ղ�����̒��ǐ�ł��B |
 |
�X���R����
|
�@
���Z�H���h�̂����u�n���h�v
�f�o�r�ʒu���͖ڕW���̑���ʒu���������\�̒��S�łȂ����R������H��̂ɕ�����₷���A
���ԏ�A�����A���ւȂǂ̏ꍇ������܂��B���̑��̏���2002�N���Ɍ��n�Ŋm�F�������̂ł��̂ŁA
���̌�A���H�g���Ȃǂɂ��ړ]��s����������@�ɂ��s�����������s�������̕ύX������̂�
���̌�̏��ł��m�F���������B