|
�Z�\�㎟ |
 |
���s�j�S���䒬 ���Z�� �i�q���C������w���� |
���Z�H-4���F�h���疼�É��h�E�{�h�܂����R���Z�\�㎟�̂����\���h�ڂŒ��R�����Z�\�Z�h�̏\�l�Ԗڂ̏h�u����h�v�����ē����܂�
|
�Z�\�㎟ |
 |
���s�j�S���䒬 ���Z�� �i�q���C������w���� |
�u����h�v���́A���哹�Ɣ��Z�H�́u�Ǖ����W�v�A�u���Z�H�����v�Ɣ��Z�̒��S�n�u����h�v�̑��싴�̎l���H�A
����h������́u����̐l���n���v�A�u����h�≮��Ձv�A�����̗��āu�T�ۉ��v�A���͈�҂́u����h�{�w�Ձv�A��{��В����A
����̐�A�����Ղ́u�ꐸ���v�A����隬��A�ʐ�T���A����h�e�{�w�ՁA�u���J���v�̂���{�����Ɛ���h���D��ՁA
�������痷�ĂɂȂ����u�����K�g�̉Ɓv�A�����L�䂩��́u���������~�Ձv�A�u�����ˁv�A�L�d�̕����G�́u���̌��t�v�A
�u���ڒn�����v�A������ׁA���H�����ɂ�����Z���{�Ղƌ䗷�_�ЁA���Z���{�Ք�̂���������A�E�����R�Õ��A
��{�Õ��A���n��ɂ���Õ��Q�A��艺���́u��铔���W�v�A�u���̃��}�����v�A�u���̓��W�v�A�t���H���W�A
�|�������q�q�����J�����w�Z�u��䮋`�Z�i�������������j�v�A�u�|�����w���Ձv�A���H���W�A
�|�������q�̕�̂���T��i����Ƃ��j���A�Ȃǂ��f�o�r�ʒu����Ƌ��ɏЉ�܂��B
|
���̕łŏЉ�����R����Ԑ}�i�Ԑ��F���R��
���F���H�j |
|
|
|
����h |
|
�h��̊T�v ���{�́E��_�˗́A�@�h���@���S�A�@�l���@1�A250�l�A�@�Ɛ��@320���A�@ ���ā@��\�����A�@�{�w�@�ꌬ�A�@�e�{�w�@�ꌬ�A�@�≮��@�O�P���A �]�˂���@�@�@�@�@�@�@�@111���W���i��S�R�Vkm�j �ԍ�h����@�ꗢ�\�O���i��ꗢ�ˁj �փ����h�܂Ł@�ꗢ���i����ꗢ�ˁj |
|
�u����h�v�͈ꎞ�u�����˗́v�ł��� �����\�O�N�i1801�N�j�����̏h��́B |
|
���m�N���摜�́u����h�v�q��ʐ^ |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
����h �@����h�́A���R���Ɠ��C�������Ԕ��Z�H�̕���_�ƂȂ�d�v�ȏh��ł��B �@�h��̒����́A��������́u���̌��t�v�����O�����́u���̌��t�v�܂ł̒������V���]�i���V�U�S���j�ł��B �@�h���̂��̓����Q�����܂�Ė��`��A�������Ŋɂ��Ȃ����Ă���A�����̌��t����{�w�A�e�{�w�����ʂ����Ƃ��o���Ȃ��悤�ɂɂ��Ă��܂��B �@����h�ɂ͐l��ו����p�����Ă�≮�ꂪ�R���������āA�T�O�l�T�O�D�̐l���Ɣn�̎�z�����܂����B �@�h���̂��߂̎{�݂ɂ́A�g���̍����l�����܂�{�w�E�e�{�w�A��ʂ̐l�����܂闷�ĉ�������܂����B �@�V�a�S�N�i�P�U�W�S�j�͂P�U�����������Đ��������P�Q�N�i�P�W�O�O�j�ɂ͂R�{�̂S�T���ɑ������܂����B �@�������R���𗷂���l�͘Q�ԍu�E�֓��u�Ȃǂ̒�h�𗊂��Ĕ��܂�܂����B �@�T�ۉ��E���l���E�O�g���E�ቮ�E�T���Ȃǂ̗��ĉ��̉������c��A�T�ۉ��͍����o�c�𑱂��Ă��܂��B �@��{��Ђ̐Β����t�߂ł͖����T�ƂX�̓��A�Z�ֈʒu���J����A�ߋ��̑吨�̐l�œ��킢�A�h��̔��W���x���܂����B �@�h��k�𗬂�鑊��́A�앝�Z�\���i���P�O�X���j�̖\���ŁA�����悭������邽�߁A���ʂȒʍs������Ƃ��ȊO�͑���̂悤�ɒ������l���n���ł����B |
�u��h�H�����G�}�v�ɂ�铖���̐���h�̉��
|
||
| ����
�{�V�̑�́A��̕����l�ɂ���B�����̌K�����s����B ��{�̒���@�z�ɐ���ʌM�ꓙ���R�F��_�Ƃ���B ��{�R�́A�݂́R���R�Ƃ��ӏ���B�Ђ͎R�̘[�ɂ���B��Ж�B�З̎O�S�B ���̗��A�����Ȃ�A�ނ����͂悫�h�Ȃ�B�i���݂̊փ��������j �������̕��ɍs�����@��Ȃ��t�ɂȂ���B �͂��ݏ���B���Ɍ�e����B�i�w�ȁu�Ǐ��v�̌̋��ł�����A�M�O���ɔǏ����������ω���������B�ڂ����́A���X�ł��u����̈ꗢ�ˁv�ɂ���j ��Ɍ{�ĎR����B |
|
����͔��Z���S�n |
 |
|
�@�@�@�@�̐�L�d�E�k�։p�a��u�ؑ]�C���Z�E�㎟�V���@�����v�i�唻�ъG�j |
|
�ꏊ�͐���́u���̌��t�v�t�߂ł� |
��قǂ��u����Ǖ����W�v�܂Ŗ߂�A���悢���u����h�v�֓���܂��B
|
�Ǖ��� |
�@
|
���싴�ԐM�������_ |
|
| �@�@�@�@�@�@����h���������_ �@���܂��đ���ɉ˂����u���싴�v��n����u����h�v�ɓ���܂��B �@�u���싴�v��n�炸�ɒ��i�������R�D�U�����قǂŖL�b������헪�Ɓu�|�������q�v�̐w���Ղ֏o�܂��B |
|
����h���싴 �s�j�S���䒬����@�� |
|
����h������ɂ�����u����v
|
���ǂł���ӏ������Ă݂܂����B |
|
|
|
�Z��n�}�ɊY���ӏ���}�����܂����B |
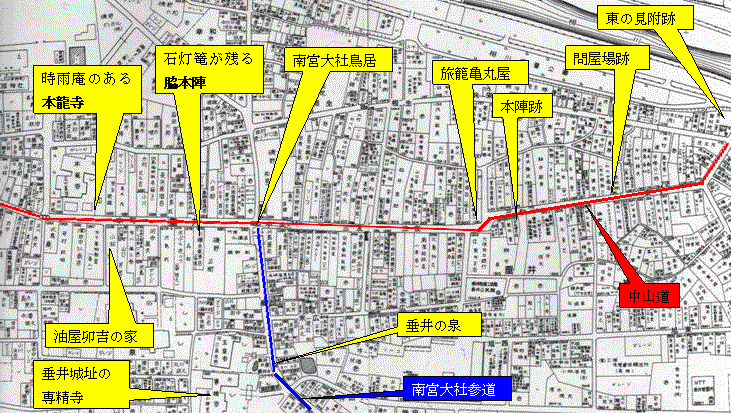
|
 |
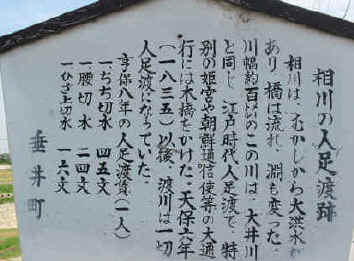 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����͋����Ȃ��l���n���̐� |
|
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̌��t |
|
|
����ɂ͖��N�t�ɂ͑�R�̌�̂ڂ肪�͂��߂��܂��B |
�܊X���ŏ��߂đ唪�Ԃ̎g�p������
����h�͊��q����ɂ́u���q�X���v�̏h��Ƃ��āA�����č]�ˎ���ɂ́u���R���v�́u���Z�H�v�Ƃ̕���_�Ƃ��ĉh���܂����B
�܂��A��{�_�Ђ́u��O���v�Ŗ����܁A��̓��ɑ咹�����u�Z�֎s�v�������A���킢�܂����B
�h��������A�����A����������A�������l�ԁi��V���j����܂����B
�����Č܊X���ŏ��߂đ唪�Ԃ̎g�p�������ꂽ�h��ł�����܂��B
|
����h�≮�� �s�j�S���䒬����@���i�����܁j1���� |
|
�≮��͎O��������A�O�����Ŗ߂܂����B
 |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@����h�̖≮�� �@�Ԍ��܁D�܊��@���s�����D�܊��̋���Ƃ́A��X�u�\��E�q��v�Ƃ�������h�̖≮�A�����Ȃǂ̗v�E���߂Ă��܂����B �@�≮�ɂ͔N��A���t�A�n�w�A�l���w�Ȃǂ����āA�ו��̉^�������d��A����̐l���n�̎�z�����Ă��܂����B �@�����̉ו��́A�K���≮��ʼn��낵�A�������\�ܐl��\�ܕD�̐l�n�ő����Ă��܂����B �ʍs�������ɂȂ�Ɖו��������Ȃ�A�����̐l�n����ĉ^�������悤�ł��B �i�u�≮��v���u�����v�ɂ��Ă��u��齊X���Ɗ}�����v���u���Z�C�v�̓n���v���Ŗ��ɂ���܂��j |
|
�����˂͒��R�����֓��鋷�����̉��ɂ���܂��B
|
������ �s�j�S���䒬 |
|
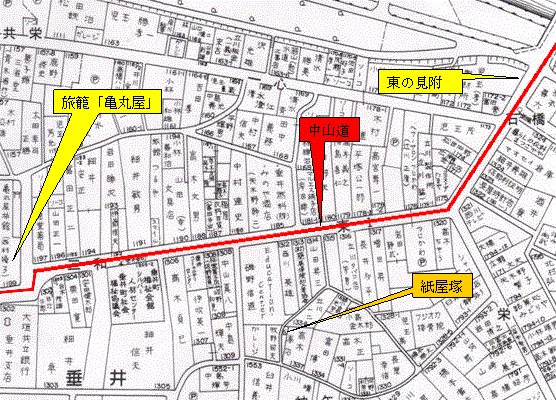 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���w��j�Ձ@�������@�i���a�R�Q�N�U���P�T���w��j |
|
|
|
|
| ���R�������������������܂��B | �R�O���قǐi�ނƂx���H�֏o��̂ʼnE�i�݂܂� |
|
|
|
| �x���H�����Q�O���قǂ̂Ƃ���ɂ���܂� | |
|
|
|
|
�@�u�����v�߂��ɂ���ꂽ�u�����ˁv�͍����c��A�����̎��_�u�������_�v���Ղ��Ă�ƌ����Ă��܂��B |
|
�����˂��璆�R���֖߂萼���P�T�O���قǂŊX�����u�e�`�v�ɋȂ���܂��B
�������]�ˎ��ォ��̗������c���Ă��܂�

|
������ �s�j�S���䒬����@�O�F�i����䂤�j |
|
 |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����T�ۉ� |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�Ƃ� |
���Ģ�ۋT���v���琼���W�O���ʂ̂Ƃ���ɖ{�w�Ղ̂���҂�����܂��B
|
����h�{�w�� �s�j�S���䒬����@�O�F�i����䂤�j |
|
���͂���҂���
�{�w���c��ł����ƌn�͌��ݑ������u�Ɓv���u��t�v�������悢�ł��B
����̖{�w�E�߂Ă����I�c�Ƃ��Ƃł����B���͈��c���Ȉ�@�ł��B
 |
|
�@�@�@�@�@����h�@�ŏ��́u�{�w�v |
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@��������ɂ͏��w�Z�Z�ɂɂȂ����{�w |
|
��������h�������ɂ͍��ǂ̋��Ƃ����т܂�
�h��̒��S�́u�����v�Łu�Z�֎s�v���B
���S�n�́u�����v�ŁA�h���ɂ͎����E�����E�݉ƁE�����E���扮�Ȃǂ̏��Ƃ�ؔҁE��H��b��E�P�����̐E�l�����܂����B
�܂��A�u�Z�֎s�v���J����Ă��܂����B�i�Z�֎s�ɂ��Ă͕Ŗ��Ɂu�Z�֎s�v�̐���������܂��j

�u�{�w�Ձv����100m�قǂœ_�ŐM���̌����_�֏o�܂��B
�����͏h�̒����́u�{���v�l�p�쑤�ɓ�{��Б咹��������܂��B
|
��{��В��� �s�j�S���䒬����@���� |
|
���̒����͍��������Ɏw�肳�ꂽ�ԛ���̒����ō����V�D�P���A���S�D�T������܂��B
�����ɐΓ��U����Η����A���W���e�ɂ���܂��B
���̔����͒n���ɖ��܂�傫�Ȓn�k�ɑς�����\���ɂȂ��Ă��܂��B
 |
|
���W�������u��{�Ё@�]�@�����v�i�W�O�O���j�Ƃ���܂��B |
 |
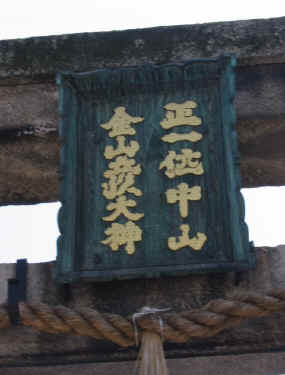 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�Ή����l�S���Ŋ�i�����咹�� �@�u����ʒ��R���R��F��_�v�̊z�́A����@�V�����u�@�@�����e���v�̕M�ւł��B |
|
��{��Ђ̒������߂�
|
����h�e�{�w�� �s�j�S���䒬����@�{�� |
|
�e�{�w�͍ŏ��͂���܂���ł������A���i�\�O�N�ɂ͌���135�i�S�S�U�u�j�A��\���A���ւ��݂����Ă��܂����B
��{��Б咹�����ɂ���܂����B
�����\�O�N�i1816�N�j������{��Б咹�����́u�����v�ɂ������ƂŁA
��������ɘe�{�w��ƌ��ւ��u�{�����v�Ɉڒz���ꌻ�݂��g���Ă��܂��B
|
�����R�{������ �s�j�S���䒬����@�{�� |
|
���ߓV��@���u�ՏƉ@�v�ƌ����܂������A�������N�i1469�N�j�@�@��l��
���Z�����i����j�̍ۂɁu��y�^�@�v�ɓ]���܂����B
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�R��͘e�{�w�̖�����@�͌��ւ����ڒz |
|
 |
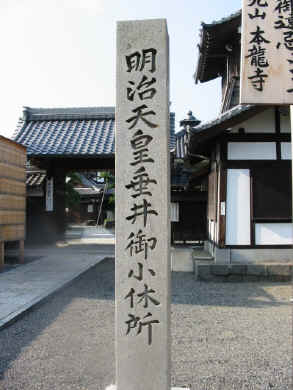 |
|
�����P�P�N�i�P�W�V�W�N�j�P�O���Q�Q�� |
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���D��� |
|
�u�{�����v�̋������O���Ɂu���J���v�͂Ђ�����Ɨ����Ă��܂�
|
���J�� �s�j�S���䒬����@�{�� |
 |
| �@�@�@�@�u�����m�ԁv�̓~������� �@���\�l�N�i�P�U�X�Q�N�j�ɔm�Ԃ͏Z�E�u�K�O�v��K�ˁA�~�����肵�� �u���́@��������߂�@���J���ȁv �Ɖr��肪����܂��B �@���͕����Z�N(�P�W�O�X�N�j�̌����ŁA�m�Ԗؑ�������܂��B |
 |
 |
|
�o��E�́u���q��v�́u�����V�v���m�Ԃ䂩��̂��̎��Ɉ�����N�i1855�N�j�Ɂu���J���v���������܂����B |
|
�u�{�����v�̌������ɂ͐�O�܂ŗ��ق��c��ł����u�����K�g�ƐՁv������܂��B
|
�������痷�ق� �s�j�S���䒬����@�{�� |
|
 |
|
�@�@�@�@�@�h�ꎞ��̑�\�I���� |
�u�{�����v�̐��̐M�������_���֓��萼�։E�܂����Ƃ���Ɂu���������~�Ձv������܂��B
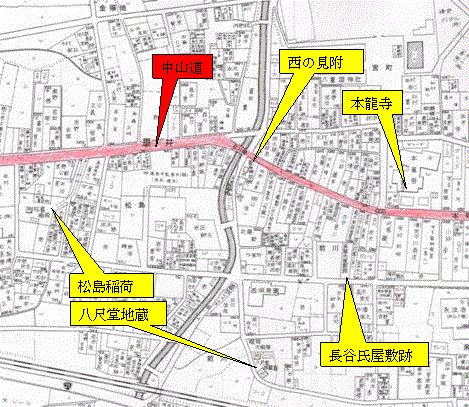 |
|
�����L�䂩��� ���������~�� �s�j�S���䒬����@�O�� |
|
 |
|
���䏊�ƂȂ������~�� |
 |
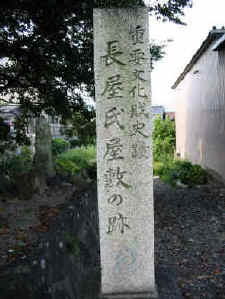 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����L�䂩��̒n |
|
 |
 |
|
���������~�Ղ� |
|
�Ăѐ���̒��̐^���𐼂֑���u���R���v�֖߂�܂��B
|
����h���̌��t �s�j�S���䒬����@�O�� |
|
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�u���t�v�̖��� �@���t�͏h��̓�����ɒu����A�h���l�͂����ő喼��u�����ٓ����v�A�u�����ᕼ�g�v�Ȃǂ̒ʍs���}�����著�����肵�܂����B �@�܂��A�����Ȃǂ��N�����Ƃ��ɂ͕����邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B |
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�u�����ٓ����v |
|
�u�����L�d�v���u����h�̊G�v�̏ꏊ
 |
|
||
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ʼn�u���R���@����h�v�̒n |
|||
�@
 |
| �@�@���ڒn�������� �@�u���̌��t�v���̓������Q�O�O���قǂɍ݂�܂��B |
|
���ړ��n���� �s�j�S���䒬����@�O�� |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�������N�|�P |
|
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���������~�� |
|
���̌�̉��C�L�^
���ۏ\�ܔN�i1730�j�����̊����ɎO�E���q����̔N���ɂ����艮�����C�����܂����B
���̌㐂��h�̖{�w�u�K���i���ʂ��͂�j�����q�̍Ȃ������̊�a�ɜ��e�n�̖���ɂ������Ă�
���Ȃ�����������ʂĂ��B
�����ŁA���̖{���ɓ����A��S�ɋF�肵���Ƃ��눽��閲���ɗ����u��̖��`�v��
������ꂻ��ɂ���ďd����a���������ƌ����Ă��܂��B
 |
 |
| �n�������N�|�Q ���̎O�����́A���\�Z�N���i1693�j�܂ł͓y���ɖ�����Ă����̂��A �߂��̂����̘a���A�o�@�̖����ɗ����u��͔��ړ��̒n���Ȃ�A�N�v�������ċ��n�̑��тɊ|������ �ꂵ���A�@���l�̑����ɂĂ��悢��F������������v�Ɨ��܂�܂����B ���͈���@������ƒf�������A�O��ɂ킽�薲���ɗ����ꂽ�߁A�����̑�H�u�㍶���q�v�ɗ��݁A ���ڎl���̂��������ĐΕ������u���܂��A���^���̉_����l�ɂ�苟�{�����ꂽ�B |
|
 |
 |
|
����ʔ��ڈ�ב喾�_�����J���Ă���܂� |
|
 |
 |
���R���֖߂萼���Q�O�O��
|
������� �s�j�S���䒬����@���� |
|

 |
 |
|
�����Q�������֓���Ɨ��h�Ȃ���ׂ�����܂��B |
|
�u���̌��t�v����700m���炢�łi�q���C���{���̓��ɏo�܂��B
����ʍs�ł��̎Ԃ͍������瓥��n��܂���B
|
�i�q���C��������̓��� |
|
 |
 |
| �@�Ԃ͉E�̓��𐼂i�ݗ�����n���Ăi�q���C���{���̌������s�ɑ���u����21�����v�֏o�܂��B �@�u����21�����v���u���R���v�ł��B |
|
�����ł�����x�h��̒��S�u��{��В����v�܂Ŗ߂��Ėk�Ȃ���A���H�����ǂ�
���Z�Z���{�ՁA�E�����Õ��A�|�������q�w�����Ȃǂ����ē��������Ǝv���܂�
 |
| �@���H�ւ͓�{��В����̂���l���H��k�Ȃ���u��K���v��n��܂��B �@���̌�͉��̏Z��n�}�ŖK�˂Ă��������B |
|
���Z���{�ՁA�䗷�_�ЁA�������A�E�����Õ��̈ʒu�} |
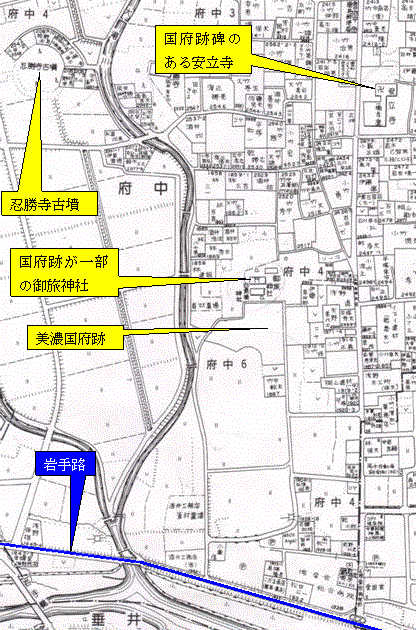 |
|
�䗷�_�� �s�j�S���䒬�{���S���� |
|
|
�䗷�_�Ћ��� |
�䗷�_�Ђ̓쑤�ɔ��Z���{�Ղ����苫������s���܂��B
|
���Z���{�� �s�j�S���䒬�{���Z���� |
|
|
�@�����R�N����X���ɂ킽�锭�@�����̌��ʁA����������P�O�O���[�g���ق� |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�Ƃ� |
�䗷�_�Ђ̖k���R�O�O���̈������̋����Ɂu���Z���{�_�Ձv�̔肪����܂�
|
������ �s�j�S���䒬�{���O���� |
|
|
���Z���{�L��ƋL���ꂽ�������̔� |
�R�� |
|
|
|
�������{�� |
�������̐��̍ד������˂��ˋȂ���Ȃ��琼���Q�S�O���قǐi�ނƔE����������܂��B
|
�E���� �s�j�S���䒬�{���l���� |
|
 |
|
�E�������琼�̋���n��ƒ����ɉE�i�k�j�ɋȂ����h����X�Om���i�ނ�
���Ƃ̊ԂɔE�����R�Õ��̈ē����K���[�W�̌������Ɍ����܁B�i�E����������P�W�O���قǂł��j
|
�E�����R�Õ� �s�j�S���䒬�{���l���� |
|
 |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�E�����R�� |
|
�E�����R�Õ��̋߂��Ɏ�{�Õ�������܂��B
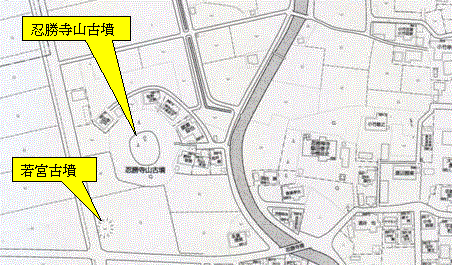 |
|
��{�Õ� �s�j�S���䒬�{�� |
|
 |
|
�E�����Õ��̂����߂��ɂ���܂� |
���Õ��͕{�����k�̕��������n���ɓ_�݂���Õ��Q�ł�
|
���Õ��Q �s�j�S���䒬��� |
|
 |
| ���䒬���@�쐣�� |
 |
 |
 |
 |
���H�̌�s���܂Ŗ߂��P�����قǐi�ނ��u�����n��v�֓���܂��B
���̒Ǖ����u��铔�v������܂��B
|
�����铔���W �s�j�S���䒬���@���� |
|
 |
 |
 |
|
�傫�ȁu��铔�v�̉��ɂ́A���̖k�̒n����ē����铹�W�������Ă��܂��B |
|
��قǂ́u��铔�v�܂Ŗ߂�k���̓����u���n��v�ւƂ�܂��B
���n��̓�����̏H�t�_�Ђ��u���䒬�w��V�R�L�O���v�̑傫�����}����������܂��B
|
���̃��}���� �s�j�S���䒬���@���� |
|
 |
 |
| �@�R�������n�u���v�Ɏ�������̂͊w�p�I�ɒ�����������̎����Ƃ��đ�ł��B �@���̂��ߐ��䒬�̓V�R�L�O���Ɏw�肳�ꂢ�܂��B |
|
�_�Ђ̘e�ɏ����ȓ��W������܂�
|
�u���v�̓��W �s�j�S���䒬���@���� |
|
 |
 |
 |
|
���@�ɐ��@�փ����@�� |
�E�@�t���@�� |
���́u��蓹�W�v��k�u�E�@�t���@���v���Q�O�O���قǐi�ނƁu�s���H�v�����蓹�W������܂��B
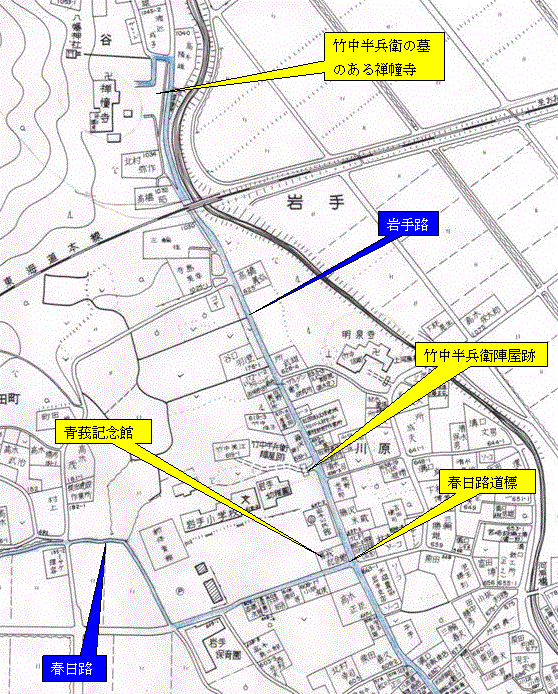 |
|
�t�������W |
|
 |
 |
 |
|
�E�@����@�� |
�E�@��Α��@�� |
���̘e�Ɂu��䮋`�Z�v�̌���������܂�
|
��䮋`�Z�i�L�O�فj �s�j�S���䒬��莚�쌴�i�����j |
|
 |
|
��䮋L�O���i���������˂�j |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�q���A���{�|���� �@�����q�̎q���́A�փ�������ł͓��R�ɑ����A���D�̗F�u���c�����v�Ƌ��Ɂu�Γc���v���U�ߐ���������܂����B �@�����͕��R�������w�����\���Z����̊��{�Ƃ��ē���ƂɎd���܂����B �@�w����D�ݗї��R�ƌ�V�[���A���������ɏG�łĂ��������Œ������u�L�Ӂv������܂��B �@�V�۔N�Ԃ��u��䮓��v�i�������ǂ��j��݂��Ɛb��̋���ɓw�߁A�����̐l�ނ�y�o���܂����B �@�����ɂȂ�u��䮋`�Z�v����u��菬�w�Z�v�ƂȂ�܂����B �@���݂́A���{�|���ƊW����ѓ����̊w�Z�����Ȃǂ��u��䮋L�O�فv�ɕۑ�����Ă��܂��B |
�Z���ɂ͑����́u���v������܂��B
 |
 |
|
���䉻���V����i���Z�h�\�ܐ��j |
��쐥�Y�V��� |
|
��䮋L�O�ق̒�ɂ�����̐����� |
|
�Ȃ��u�|�������q�w���Ձv�łȂ��u�|�����w���Ձv���H
|
�|�����w���� �s�j�S���䒬��莚�쌴�i�����j |
|
 |
 |
|
�|�������q�d���� �@�L�b�G�g�̌R�t�Ƃ��Ė������|�������q�d���͓���ė��Ƃ������u�q�d�A�_�̔@���v�Ə̂��ꂽ�B�@�����q�������Ȃ��l�X�̐S�𑨂���̂́A��z�����m���A���@�́B�@��������Ă����_�~�S�Ȃ��A������]�܂��A�s�}���ɂ��ĎႭ���|��A�R�t�̔��w�ɐ��������U�ƌ����Ă��܂��B |
|
 |
| �@��������ؑ����Ǔh��̘E��A����A�������Đ��ʂɂ���u�ډB���Ί_�v�E���E���͂̐Ί_�Ȃǂ������̖ʉe���Ƃǂ߂Ă��܂��B |
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����q���̒m���A�\����� �@�����q�͗c��������w���D�݁A�����̕��@�����w�сA���Â��Ȑl���́A�헐�Q��������ɐ����镐���Ƃ��ẮA����Ȃ��v���܂����B �@�d���Ă�����N�u�֓������v��Ɛb���������u�����ҁv�Ƃ����}���ꂽ�B �@�i�\���N�i1564�N�j����Ȕ�]�𐁂�������Z�ɔ����q����ƑS���ɂ��̖���m�炵�߂�����Ƃ́A�֓����O���z�����A��U�s���̏��u��t�R��D�掖���v�ł���܂��B �@���̍��V����_���Ă����D�c�M�����A���̕�����Z���̔�����^��������ŁA���̏�̏��n��\�����ꂽ���A �����q���u��N���Ђ߂邽�߁A������厖�����s���������ŁA�����͎�N�����ɕԂ������v�ƌ����ċ��ۂ��܂����B �@���̈ꌏ�ŁA���܂Łu�|�������q�v���y�����Ă������͂̊�͈�ς��܂����B |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�G�g�Ɣ����q�� �@�V�����N�i1579�N�j�A�O�؏�i���Ɍ��j�U�����ɓ|��A�G�g�̊��߂ɂ���ċ��s�Ő×{���Ă������A�Ăѕa�������ĕ���̐��ɂ��ǂ�A�Z���\�O���O�\�Z���Ŗv���܂����B |
 |
 |
|
�@���������u�ډB���Ί_�v�������܂��B�@�����Ă͂��̌������ɐw�����������̂ł��傤�A���͊��c�t���ɂȂ��Ă��܂��B |
|
�u�w���Ձv����k���P�O�O���قǐi�ނƓ��W������܂�
|
������̓��W �s�j�S���䒬��莚�쌴�i�����j |

�u��v�́A�������琼�̕��n��ɂ���|�����̋����u���R��v�����������ł��B
�����q�̎q�u�d��v�͊փ���������u�ƍN�v����M�����݂Ƃ߂���ܐ���̏��̂�����
�u���R��v���炱�̒n�։���w�����\���܂����B
 |
| �@�@�@�@�@�@�@�E�@��@�@�@���@�t���A���䓹 �@�u�|�������q�v�̕�̂����u�T�����v�i����ǂ����j�́A �k�̓��C���{��������̃K�[�h�����������������ɂ���܂� |
|
�i�q���C�����K�[�h �s�j�S���䒬��莚�쌴�i�����j |
|

|
�u�|�������q�v�̕� �s�j�S���䒬��莚�쌴�i�����j |
|
 |
| �@�@�@�@�@�d�B�i���Ɍ��j�O�ɂ������|�������q�̕���ڂ� �@���̎��́A�����O�N�i1494�j�F�����i���������j����̐������ׁi�������傤�����j�a�����J�n���܂����B �@�V�����N�i�P�T�V�X�j�d�B�i���Ɍ��j�O�̐w�ŕa�����܂������A�����̕�́A�O�ɂ�������j�d������ڑ��������̂ł��B |
 |
 |
| �@���݂̖{���́A�����q�̑��A�d����������O�N�i�P�U�U�R�j�Ɍ����������̂ŁA���w��G��u�|�������q���v������܂��B | |
 |
 |
| �@ | �@ |
 |
 |
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�������q�d���̕� |
|
������x����h��̒��S�u��{��В����v�܂Ŗ߂��č��x���u��{��Ёv�֎Q�q�������Ǝv���܂��B

��{�_�Ђւ͒������������ē�ցu�����v�i�W�O�O���j�ɂ���܂��B
�X���R����
|
�@�喼�̒ʍs�̖ړI�̑������A�Q�Ό��Ƃ����Ď����̗̒n�ƍ]�˂̊Ԃ��P�N�����ɉ�������]�˖��{�̐��x�ɂ����̂ł����B |
�f�o�r�ʒu���͖ڕW���̑���ʒu���������\�̒��S�łȂ����R������H��̂ɕ�����₷���A
���ԏ�A�����A���ւȂǂ̏ꍇ������܂��B���̑��̏���2002�N���Ɍ��n�Ŋm�F�������̂ł��̂ŁA
���̌�A���H�g���Ȃǂɂ��ړ]��s����������@�ɂ��s�����������s�������̕ύX������̂�
���̌�̏��ł��m�F���������B